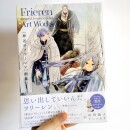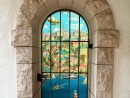半導体強国だった日本、専門家「日本は間違いを犯した」―台湾メディア
拡大
23日、台湾メディアの聯合新聞網は日本の半導体産業の変化について専門家の分析を紹介した。
2025年5月23日、台湾メディアの聯合新聞網は「1990年代まで世界の半導体市場を席巻した日本がなぜ今、台湾積体電路製造(TSMC)をリスペクトするほど競争力が落ち、他国に追い抜かれたのか」について専門家の分析を紹介した。
記事は、台湾の経済誌記者として30年にわたりTSMCと台湾半導体産業の歴史を追い続けてきた林宏文(リン・ホンウエン)氏が著作やポッドキャストなどで言及した内容を基に、日本の半導体産業の競争力の変化について六つの切り口から論じた。
一つ目は「日本の半導体の没落」で、記事は「歴史を振り返ると、日本は80年代、90年代に世界の半導体市場を主導していた。そのことが米国の強い関心を引き付け、日米半導体協定の締結に至り、円高や100%関税、特許技術の開放などの政策で半導体産業全体に大打撃を受け、競争力の低下と他国に追い越される羽目になった」と指摘した。
二つ目は「内憂外患」で、記事は「統計によると、90年代の半導体業界で世界の10大企業に6社も入っていた日本企業が23年時点では1社も入っていない。日本の研究者によると、日本は『外患』以外に『内憂』もあり、それは技術開発を過度に求めすぎて、市場の本当のニーズに気づいていなかった点だろう。日本には高性能の電気鍋がたくさんあるのに、一番売れるのはシンプルな機能に絞った台湾の大手総合電機メーカー・大同グループ(TATUNG)の電鍋(万能調理器)だったのが良い例だ」と述べた。
三つ目は「完璧主義の追求が変化のスピードを落としたこと」で、記事は「日本人は何事にも厳粛で、研究開発にも真面目だったが、市場の変化に対する対応速度が欠乏していた。そこに完璧主義が加わり、製品やサービスが120%にならないと市場に出せなくなった。そうして、市場に出した頃にはとっくにニーズやブームが過ぎ去り、他国に取って代わられてしまった」と指摘した。
四つ目は「日本企業の決裁フローの硬直化」で、記事は「台湾の一般的な企業の『ボスが言うならOK』という風潮とは違って、日本企業は『多数決で共有』で、煩雑な決裁フローを取りがちだ。かつて林氏は日本の友人から、1冊の企画書に40個もの審査の認印が押されている写真を送られたことがあるという。一般社員の提案が段階を経て上がって行き、最終的に社長が決定しているということだ。このような組織は硬直化している。特に変動の速い情報産業では数カ月もたたない間により新しくより快速なサービスや製品が生まれる。日本企業にとってはそれは大きな試練となる」と指摘した。
五つ目は「日本企業とラピダスの挑戦」で、記事は「日本にも組織の硬直化に対する問題意識を持つ企業は一部存在する。加えて今は多くの新しい企業が誕生しているため、対応や調整をしていることだろう。日本の半導体業界の希望とされるラピダスが成功するのは難しいと見ている。日本政府やラピダスを構成する日本企業8社が資源を大量投入しても、27年までに目標を達成するのは挑戦的と思われる。お金を稼ぐというより、自給自足が達成できれば、成功と言えるだろう」と論じた。
六つ目は「台湾半導体産業の優勢」で、記事は「日本と比較して、台湾の半導体産業はファウンドリを中心として、市場変化への柔軟かつ快速、臨機応変な対応を頼みに世界のサプライチェーンにおいて不可欠な存在となった。台湾の中小企業文化の決裁の速さは、日本の多数決共有決裁方式と比較して、より早く市場のチャンスをつかむことができる。また、TSMCの成功は技術力だけでなく、サプライチェーンへの協力を惜しまず、例えばオランダの半導体製造装置大手ASMLのような、各国のより良い企業と協力できる方式にもある。この点が日本企業からもTSMCをうらやむ声がある理由だろう」と指摘した。(翻訳・編集/原邦之)
関連記事
大阪万博の会場で虫が大量発生、中国ネットの反応は…
Record China
2025/5/23
<卓球>6-10から怒涛の6連続ポイント!孫穎莎「試合では一瞬で状況が変わる」
Record China
2025/5/23
「日本の文明に衝撃受けた」との投稿に中国ネット賛否=「確かに優れている」「神格化するなよ」
Record China
2025/5/23
「コメ高きこと金のごとし」、コメ好き日本人もパンに切り替え―台湾メディア
Record China
2025/5/23
韓国の登山道に設置された看板に「非常識にも程がある!」と非難殺到、その内容は?
Record Korea
2025/5/22
夏休みシーズン、日本行き航空券が前年比5~10%値下がり―台湾メディア
Record China
2025/5/22