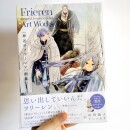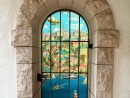豆蔵AIテクニカルセクターが論文発表、生成AIの「自分で間違っているとわかるにも関わらず間違いを出力する」現象を発見
株式会社豆蔵(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:中原 徹也、以下 豆蔵)が生成AIの研究論文を発表したことをお知らせいたします。豆蔵のAIテクニカルセクター所属の石川 真之介、藤堂 真登、立教大学大学院人工知能科学研究科(所在地:東京都豊島区、研究科委員長:大西 立顕)による研究グループは、大規模言語モデル(Large Language Model, LLM)が、与えられた情報に対し、実際には存在しない誤った規則性を見出してしまうことがあると発見しました。特筆すべきは、そのような誤った規則性についてLLM自身に検証を行わせたところ、「その規則性は存在しない」と正しく判断できる場合も少なくないことが分かりました。つまり、LLMは自ら誤りであると判断できる規則性を、存在すると主張してしまうことがあるということです。
このような挙動は、社会においてLLMを活用していく際に問題となる可能性があります。
この成果をまとめた論文“The Idola Tribus of AI: Large Language Models tend to perceive order where none exists”が、計算言語学会(Association for Computational Linguistics, ACL)が主催する、自然言語処理分野を代表する国際会議の1つである The 2025 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing(EMNLP 2025: https://2025.emnlp.org/ )にFindings(本会議での採択に次ぐカテゴリ)として採択されました。中国・蘇州にて開催されるEMNLP 2025にて、2025年11月5日に発表しました。
■生成AI活用と論理的思考力
LLMを含む生成AIが広く社会で活用されるようになりつつあります。LLM活用においては、LLM自身がもともと持っていない、社内の情報などを参照して応答をできるようにするRetrieval-Augmented Generation(RAG)、LLMに外部システムと連携させる等して複数のステップが必要なタスクを実行させるAIエージェント等、様々な活用技術が発展しています(参考:AI技術チームによる技術発信 第16回:AIエージェントとは ―その定義と活用例のご紹介― https://www.mamezou.com/techinfo/ai_machinelearning_rpa/ai_tech_team/16 )。
LLM活用にあたっては、必要な知識を参照できる場合に、LLMが適切な応答、判断ができることが前提となります。そのために必要と考えられるのが、LLMの論理的思考能力、すなわち情報に基づいて論理的に判断を下す能力です。もしLLMの論理的思考力が十分でない場合には、RAGやAIエージェントの枠組みにおいて適切な情報を参照できた場合でも、誤った応答、対応をしてしまうリスクがあることになります。
LLMの論理的思考力を評価する試みはこれまで多数行われてきていますが、「この結論はこの前提から導出可能か」という、演繹能力に注目したものが中心でした。一方、社会における現実的なタスクに対応するためには、演繹能力だけでなく、与えられた情報から状況の全体像を把握する、帰納的な側面についても対応できる能力が必要です。
■LLMの論理的思考力の評価
われわれは、これまで注目されてこなかったLLMの純粋な論理的思考力の帰納的な側面について評価するため、事前知識の有無の影響を受けない、「数列から規則性を導く」というタスクを設定しました。具体的な問題設定をしてしまうと、知識の欠如により誤った出力をする現象(ハルシネーション)との区別が曖昧になります。数列の規則性という、事前知識の必要ない認識タスクを評価することで、情報獲得とは独立に論理的思考に対するリスクを評価できます。
実験の結果、評価した5つのLLM(OpenAI o3, o4-mini, GPT-4.1, Meta Llama 3.3, Google Gemini 2.5 Flash Preview Thinking)の全てにおいて、存在しない規則性が存在すると主張することがあることがわかりました。
評価したLLMの中では誤りが比較的少なかったo3について、出力された誤った規則性が本当に存在するのかを検証させたところ、そのような規則性は存在しないと結論づけることが少なからずありました。これは、o3モデルが「自分自身で誤っていることがわかるにも関わらず、存在しない規則性を出力することがある」ことを初めて系統的に示した結果となります。
今回発見した、情報不足ではないにも関わらず誤った出力をする場合があるという事実は、LLM活用において大きなリスク要因となる可能性があります。LLM活用においては、どのようなリスクがどの程度発生しうるかを評価し、可能な限りリスクを低減する方策を検討し、残ったリスクを許容できるかどうかを見極めることが必要となると考えられます。
■豆蔵の生成AI活用関連サービス
豆蔵では、AIエージェントの検討・実装を含む生成AIの活用支援サービスを提供しています。生成AIの導入検討からRAGシステムの構築まで、貴社の課題及び環境に合わせ、リスクの評価も行いながら最適なソリューションをご提案いたします。
また、システム開発の上流工程を生成AIを用いて支援するサービス「おしごとモデルズ(R)」を提供しています。「おしごとモデルズ(R)」により、「だれでも」「かんたんに」要求開発を行うことができます。
生成AI関連以外でも、先端的なAI技術を用いたデータ利活用支援サービスを提供しております。AI技術チームのメンバーをはじめ、最新の技術に対する知見を持ち、実務としてのAI技術活用の経験豊富なコンサルタントが、貴社の課題解決をお手伝いいたします。
■豆蔵AIテクニカルセクターについて
豆蔵では、AIに関する独自技術を含む専門的知見を、特定のサービス領域だけでなく、豆蔵が提供する各サービス領域と連携するため、全社横断的なAI事業の中核組織である「AIテクニカルセクター」を設立しています。今回論文発表する研究成果をはじめとする先端的なAI技術の活用を、幅広いサービスにおいて展開していきます。
■論文情報
Shin-nosuke Ishikawa, Masato Todo, Taiki Ogihara and Hirotsugu Ohba 2025, “The Idola Tribus of AI: Large Language Models tend to perceive order where none exists.”
会議収録: https://aclanthology.org/2025.findings-emnlp.681/
Arxiv : https://arxiv.org/abs/2510.09709
■関連情報
- 豆蔵デジタルホールディングス、子会社統合を機に事業横断型「AIテクニカルセクター」を新設 ~Tier0.5企業を目指す戦略を加速し、AI事業で産業DXを強力に推進~
https://mamezo.tech/n/10765/
- AI技術チームによる技術発信 第16回:AIエージェントとは ―その定義と活用例のご紹介―
https://www.mamezou.com/techinfo/ai_machinelearning_rpa/ai_tech_team/16
- 豆蔵 生成AI活用支援
https://www.mamezou.com/services/strategic/genai_consul
- 豆蔵 『おしごとモデルズ(R)』要求開発モデリングサービス
https://www.mamezou.com/services/strategic/modelingservice
- 豆蔵 『データサイエンス・エンジニアリング支援サービス』データ利活用支援
https://www.mamezou.com/services/strategic/dataoffice
- ジュビロ磐田アカデミーにおける生成AIを活用したコーチングノウハウの蓄積と活用
https://www.mamezou.com/techinfo/ai_machinelearning_rpa/jubilo20250117
【株式会社豆蔵 概要】
所在地: 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビルディング34階
設立 : 2020年11月
代表者: 代表取締役社長 中原 徹也
資本金: 130,714,250円
URL : https://mamezo.tech/
詳細はこちら
プレスリリース提供元:@Press
関連記事
世界自動車販売で3位の韓国メーカーが中国市場で淘汰されつつある―中国メディア
Record China
2025/11/11
「ハクサイ無料」とのデマ動画拡散、数百人が畑に押し寄せ持ち去る=管理者「止めようがない」―中国
Record China
2025/11/11
韓国で日本のアニメ映画の大ヒット後に映画館離れ=韓国ネット「最近の韓国映画はつまらない」
Record Korea
2025/11/10
そろそろ「中国に責任を押し付ける」ことをやめるべき―豪メディア
Record China
2025/11/10
日本への「買春ツアー」拡大?高市首相も対策を明言=韓国ネット「いまさら?」「日本も韓国も…」
Record Korea
2025/11/10
地下鉄車内で女性の服が燃える、モバイルバッテリーが発火―中国
Record China
2025/11/10